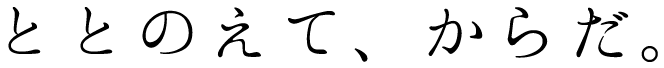睡眠不足の影響は健康面やダイエットにも及びます。太る原因のひとつともなる「睡眠不足」。上手に解決していくのは難しいかもしれませんが、身体の仕組みを知ることで解決の糸口が見えてきます。今回は私が実践している具体的な解消方法や食べ物に関する情報などをお届けしたいと思います。睡眠が上手に取れるようになると毎日が活気付きますよ!
睡眠不足の原因は?

日頃睡眠不足でもお仕事を頑張っている皆さん、本当にお疲れ様です。ハードワークでも休めないと、どうしても睡眠を削ってまで仕事をしてしまいますよね。
ですが、睡眠不足の原因は「時間」にはありません。もちろん最低限の睡眠時間は必要ですが、ある程度睡眠時間を確保しているのに
・眠っている気がしない
・疲れがなかなか取れない
・朝起きるのが辛い
という人が多いように感じます。それはお客様とのセッションでも感じることです。
まずは睡眠不足の原因を2つの観点から見ていきます。
リズムの崩れ
人体には「生体リズム」というものがあります。
地球上のあらゆる生物は、24時間を基礎として生活するリズムを持っており、人間にも同様の機構がある。この「生体リズム」に関する発見は最近特に多く、日常生活や健康と結びつけて解説されると、自己体験を通じて納得できることも多々ある。
良く言われるのが体温のリズムなどです。朝は体温が低く、日中は高くなります。このリズムを上手に活用出来ないと睡眠とリズムの調和が崩れ、「本来身体や脳を休める時に休めない」ということが起こってしまいます。川の流れと違うことをしてしまうような感じです。
日中極端な眠気に襲われたり、夜にいきなり目が冴えたりする人はリズムが崩れている証拠。私は夜に目が冴える人でした。
リズムの崩れがある人は一度生活を見直して、リズムを整えていくとこれらの症状は解決する可能性があります。
食べ物の崩れ

食べ物には栄養があります。睡眠に当てはめていうと、深い睡眠の助けになってくれる栄養が採れる食材があったり、睡眠導入剤のような役割をしてくれる食材があったりしますが、睡眠不足の人はこれらの食材を継続的に摂取していないこともしばしば。
お菓子を良く食べていたり、単品でお昼を済ませたりする人は食べ物の崩れがあるかもしれません。
睡眠不足解消に「時間」は関係ない?
これらのことから分かるように、睡眠は「時間」ではなくて、いかに自分で睡眠の「質」を崩さないようにするかがポイントになります。
生体リズムを理解して、休むべき時に休み、動くべき時に動く。具体的なポイントは次から紹介していきますが、そういったことを知ることで睡眠時間が取れないという時も上手にセルフコンディショニングをしていくことが可能になります。
睡眠不足の解消方法を区切って見てみよう

それではここからは具体的に睡眠不足の解消方法を見ていくことにしましょう。
といっても睡眠不足の解消には、シンプルに「生活を整えていくこと」が大切になります。よって、1日の生活を区切って考えていくことにしましょう。
寝る前、起きる時、日中というように分けて見ていきましょう。
寝る前は上手にスイッチを入れることに注力
寝る前は昼間活動している時に働く「交感神経」から「副交感神経」というリラックスモードの時に働く神経に切り替えていくことが大切です。そのために実際に私が普段行なっていることと重ねて説明していきたいと思います。
出来るだけ「頭を使わない」ことをルーティンにする
ポイントとしては
・頭を使った作業をしてしまうと脳が興奮しまってなかなか寝付けないこと
・ルーティンにすることで脳が「これから私は寝るのだ」とスイッチを入れてくれる
です。頭を使う作業というのは難しい問題に取り組むような学習であったり、あれこれを悩みで考えをぐるぐるさせることなど。脳を興奮させるという意味では寝る前のスマホチェックなどはあまり好ましくないです。
私は入浴する前に部屋の灯りを全て白熱灯に切り替えています。そうして入浴→着替え→歯磨き→ストレッチ→(たまに)深呼吸(政木和三氏の著書内の1分1呼吸を参考に行なっている。)という順番で睡眠に入っています。
深呼吸は交感神経から副交感神経に切り替える方法として有名ですよね。色々な所で言われているかと思います。
取り組める範囲でルーティンを作り、部屋の環境も寝るモードにしてあげると上手に睡眠に入れると思うので試してみてください。
また、私は毎日その日のことを日記に書いているのですが、この日記も実は曲者でした。今までは寝る直前に書いていたのですがある日ふと仕事終わりに日記を書き、夜は上に挙げたルーティンでそのまま睡眠。すると次の日の目覚めが良くなったのです。
1日の振り返りをしていて良い習慣と思っていたことがタイミングによっては睡眠の妨げ(意外と頭を使うんでしょうね)になっているのだなあと感じた出来事でした。日記を書いている人はタイミングや書く内容に注意すると睡眠の質が上がるかも。
次の日起きる時間を「唱えておく」こと
人間はホルモンの働きにより体内の状態を調整しています。特に目覚めと関係するホルモンは「副腎皮質刺激ホルモン」で、脈拍や血圧を上昇させます。要は「活動モードへの切り替え」を行なってくれているわけです。
目覚ましなしで起きられる、つまり「自己覚醒」できる人は、目がさめる1時間前から、心地よく目覚めるのに欠かせない「副腎皮質刺激ホルモン」の分泌が緩やかに上昇し始め、気分良く目覚めることが出来た。
この副腎皮質刺激ホルモンを分泌するためには、次の日に何時に起きるのかを強く想うだけで良いといいます。これは携帯のアラームとかではなくて、実際に自分で「想う」ことが重要。
そういえば昔、『伊東家の食卓』という番組で起きたい時間の回数だけ枕を叩くという方法をやっていたような・・・。ああいった方法が副腎皮質刺激ホルモンの分泌に役立っていたということですね。
起きたらやっぱりアレの力を借りる

起きたらまずすること。当たり前のことかもしれませんが、やはり「お日様」の力を借りましょう。
私たちの体には、体内時計というものがあります。そしてこの体内時計は光を感知してからが1日のスタートとする仕組みがあります。
それと関係するのがメラトニンという物質。身体が光を感知すると(感知場所は脳の視交叉上核と言われています)、脳の松果体という場所がメラトニンの分泌を止めてくれます。私たちはこのメラトニンお分泌を身体が感じ、眠いと感じるのです。
部屋の電気ではダメなの?と思うかもしれませんが部屋の明るさでは足りないんですね。
暗くなると松果体にメラトニンを分泌させますが、その「暗くなる」の基準は500ルクスです。<中略>大抵のオフィスは、500ルクス程度の明るさでしたよね。
ちなみに窓際に行って日の光を浴びるだけで5000ルクスもの明るさを身体に届けられることになります。蛍光灯とお日様の光の違いがありますよね。しっかりとお日様の光を浴びて、メラトニンの分泌を止めることが必要です。
海の波が引いた分だけ押し寄せてくるように、メラトニンも分泌を止められた分だけ夜の分泌が多くなります。ということは睡眠が深くなるということ。お日様の光を必ず浴びるという誰にでも出来ること、明日からやりたいですね。
日中必ず1度はやってほしいこと

さて、朝に光を浴びてしっかりメラトニンの分泌を止めたら、次は日中の過ごし方です。
私は、眠気の度合いの高低はあるにしても、食事の摂り方に関わらず昼下がりに眠くなるのが不思議でたまりませんでした。
どうもそれは脳の仕組みからそうなっているらしく、先ほど紹介した『あなたの人生を変える睡眠の法則』から引用させて頂くと、人間の脳は起床から8時間後に眠くなるように出来ているようです。
なるほど、だからいつも14時前後に急に眠気が襲ってくるのだなあと納得しました。ということは、この眠気が来る前に少し脳を休ませることをすれば良いですよね。要は「仮眠」をしていきましょうということです。
ただこの仮眠にも様々種類があります。各々のお仕事の環境によっても使い分けると良いと思います。
眠気を拭い去るだけならマイクロナップ
2分〜5分ほどの仮眠をマイクロナップと言います。これだけの時間目をつぶって視覚をシャットアウトするだけでも脳は休まります。
ただ、眠気のピークである14時ごろ(私の場合の起床8時間後がそれくらい)に必ずそれをするというのは人によっては無理ですよね。
ということで、昼食時にマイクロナップをついでに行なってしまうのが良いかと思います。もちろん満腹だと胃腸の疲れからも眠気が来てしまうので腹八分目ということもお忘れなく。
ちなみにこの時も「自己覚醒法」を使って「何分後に起きる!」と思うと意外とすっきりと目覚めることが出来ます。
時間を取れる人はミニナップやパワーナップを!
5分〜20分までの仮眠をミニナップやパワーナップと言います。これくらいの仮眠が取れると、体力や思考能力も回復するので、残りの仕事の効率もグンと上がることでしょう。
NASA、Google、Appleなど世界の一流企業や組織も続々導入をしていることで有名な「パワーナップ」。より詳しくは本に譲りますが、環境が許す人は是非導入してみてはいかがでしょう。
まとめると
まとめると以下のポイントになります。「何が何だかわからない!」という人はシンプルに以下のことを実践してみてください。
・夜は「頭を使わずスマホを見ず」で暮らす
・何時に起きるか強く思ってから寝る
・朝はしっかりお日様の光を浴びる
・起きてから8時間以内に1度マイクロナップやパワーナップを実践する
次からもっと細かい食事などについて言及していきます。
睡眠不足解消の食べ物!やはり和食は強かった

ここまで、行動として大切なポイントを述べて来ましたが、今度は食べ物でも改善を目指していきたいと思います。
睡眠不足解消に大切なポイントは「トリプトファン」と「グリシン」です。この2つを上手に摂っていきましょう。
日本古来のあの食品にトリプトファンが!
トリプトファンとは必須アミノ酸のひとつです。アミノ酸とは人体の構成に使われる大切な大切な栄養素。
トリプトファンは睡眠に関わるメラトニンを作り出すセロトニンの生成に関わります。
そのトリプトファンをしっかりと食事で摂取していくことが睡眠の質を向上させるのには大切です。
さて、そのトリプトファンが何から摂れるのか。代表的な食品としては「納豆」です。
もちろん納豆以外にもトリプトファンが含まれている食品はたくさんありますが、手軽に摂れるものは納豆でしょう。
あとはナッツ類や枝豆、かつおやまぐろの赤身、お肉などに多く含まれています。
もうひとつ重要なアミノ酸「グリシン」
もうひとつ睡眠に関係し、摂取を推奨するのがグリシンというアミノ酸です。
このグリシンがしっかり摂取出来ていると、深い睡眠であるノンレム睡眠が深くなることが分かっています。要は睡眠の「質」に関わる栄養素と言って良いでしょう。
さて、このグリシンが摂取出来る食品はえびや貝などの魚介類、アーモンド、ごまなどがあります。そしてここでもトップではありませんが「納豆」がランクインしてきます。納豆は本当に万能ですね。
[blogcard url="https://takuyakonno.com/251/"]
こちらの記事でも書いたのですが、「ちゃんと食べる」ことが良い睡眠にも繋がるということですね。
栄養に関してはこの2つをしっかりと摂取していくことを心がけましょう。
睡眠不足解消には「休日の寝溜め」が良い?

よく睡眠不足の人から「休日に寝溜めしてるんで大丈夫です」ということを聞くのですが、休日の寝溜めは果たして効果があるのでしょうか?
結論から言ってしまうと、効果はありません。筋トレと同じように、一気にやっても意味がなく、やはり「定期的に」というある程度のリズムが大切になります。
更に、寝溜めをして起床時間を崩してしまうと、最初に挙げた「生体リズム」が崩れてしまいます。これを戻すのがなかなか難しい。それが「月曜日なかなか起きれない」という現象に繋がるのですね。
そういったことからも、睡眠不足を感じている人は「少し長めに仮眠を取る」というくらいにして、いつも通り過ごすことをおすすめします。仮眠というくらいなので60分程度に納めることができれば良いと思います。
睡眠不足解消グッズについて

寝るための環境作りという観点から言うと、寝具をしっかり選択することは睡眠の充実につながります。
色々私も変えて来ましたが、1番変化を感じたのは「マットレス」と「パジャマ」かなと思います。
マットレスは枕との関係もあるかと思いますが、実際に寝て見て、寝返りが打ちやすいかどうかで決めると良いと売り場の専門の方がおっしゃっていました。マットレスを変えるのであれば実際に足を運んで決めることをおすすめします。
パジャマに関しては良い変化から気付いたのではなく、スウェットで寝るのが日常化し、ある時「そういえばパジャマを着ていた頃はぐっすり寝ていたな」という気付きがありました。
「スイッチを入れる」という点からも、やはりパジャマを着るというのはとても大切な要素でしょう。お客様の例でいうと、少し値は張りますがシルクのパジャマが「とても寝返りをうちやすくてびっくりするくらい寝心地が良い」とおっしゃっていたので参考にしてみては。
私も今年はシルクのパジャマを購入しようと考えています!
まとめ
以上、睡眠不足の解消方法とは?食べ物や休日の過ごし方、寝る前のポイントなどの具体的方法!でした。
人生の3分の1を占めると言われる睡眠。これを質の良いものにしていくだけでも、人生が変わるといっても過言ではありませんよね。
寝る前、起きる時、日中のポイントを押さえ、良い睡眠を作り上げていきましょう。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。