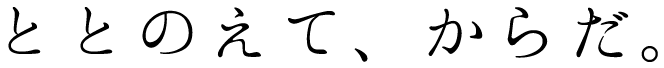運動をする人にとっては、口にすることの多いキーワードでは無いでしょうか。
骨、関節、筋肉。
特に「筋肉」なんかは、トレーニングと言えばこの話題!というくらい耳にする言葉です。
この3つの”役割”って、なんなんでしょうね。
ずーっと考えて来てて(もちろん教科書では習いましたけど)、あ、こういうことかなという思いが最近湧いているので忘れないようにメモをしておきたいと思います。
骨は身体を支える役割
これはまあそうでしょうね。一般的な女性の、片方の脛の骨だけで80kgもの重さに耐えることが出来ます。ということはその時点で「立ってるのが辛い」というのは姿勢の崩れの兆候・・・。
そんな骨ですが、関節によって動きが出ると位置が変化します。
関節が動きを作る
関節は場所によってその形状が様々あります。単一方向への動きだけであったり、複雑な動きも出来るような関節もあったり。
関節の主な役割としては、動きを作ることだと私は感じています。ここは次の筋肉の役割とセットでお話しする必要があるので次に筋肉の役割です。
動きが作られ、その中でも姿勢の保持・維持をするために筋肉は働く
まず、関節が動きを作り出します。(例えば右手を地面と平行に上げる動作を例に取ります。)
そうすると、骨の位置が変化します。(右の上腕骨から先が外転方向へと上がっていきます。)
本来、ここで筋肉がなければ、骨の重さによって右に倒れます。(人体模型なんかでやると明らかだと思います。)
そこで、その中でも倒れないように筋肉は働いています。
このヒントとなったのが、私が学生の頃に部活として行ってきた陸上競技です。
陸上競技の、特に短距離走のスタートは、爆発的な瞬発力が必要とされています。
私も短距離やハードルを専門としていたのですが、そのスタートが上手に出来た時というのは、
私の感覚の中で「あまり力が入っていない状態」でした。
ただただ前に足を出しているような、なんというか、上手く重心を崩しているようなそんな感じです。
ふくらはぎや大腿前部で力の限り蹴る様なスタートをすると、うまく身体を運べず、結果記録も芳しくありませんでした。
これに関しては為末大さんもTwitterで言及されていました。
スタートダッシュは前足後ろ足に均等に体重をかけるのではなくて、前足に8割ぐらいかけます。スタートは蹴って進むと思われますが、半分は前に転ぶ勢いを利用して走っています。ですので、スタートで転ぶぐらい前に体重をかけておいた方が有利です。
— 為末 大 (@daijapan) 2015, 10月 6
要は、スタート時は積極的に重心を崩し、それでも倒れないようにするために(姿勢維持・保持)、筋肉が収縮や伸張するということです。
ここに私は”フィットネス”におけるヒントがあるかと思っています。
何事も”使い分け”する視野の広さを
少し難しい話しになります。
意識次第で人は、同じ”肘を曲げる”という動作でも「関節主体」なのか「筋肉主体」なのかを分けることが出来ます。
関節主体の場合には、もちろん肘関節に意識を置いておきます。
筋肉主体の場合は、力こぶの筋肉に意識を置いておきます。
これをどう「使い分ける」のか。
例えば、
・筋肉をつけてモリモリになりたい!という男性
・筋肉が足りないからもう少しつけてラインをしっかりさせたい!という女性
こういう方々に案内する時は「筋肉主体」で案内します。
逆に「関節主体」となるときは
・動作そのものを改善したい
・パフォーマンスを向上したい
という時です。いわゆる今フィットネス市場でよく聞く”ファンクショナル”というのもここに入ると私は思っています。
私も自分のトレーニングにはこの考え方を生かし、今どっちのトレーニングなのかということを常に意識しています。そうすることで目的意識もはっきりとするからです。
パフォーマンスも、例えば「関節主体」からスプリント動作の向上を考えた場合
・100mのタイムを0.2秒上げる為に、今以上の重心の崩し(移動)を起こす必要がある。
・その中での姿勢維持・保持を出来るだけの筋の収縮能力や伸張能力がポイントとなってくる。
・今現在、その運動レベルにおいて、動作の邪魔となっている部分や、運動中の姿勢保持・維持に足りない部分はどこ(関節)か。
・その関節は単一の部分として足りないのか、もっと広い範囲を伴って足りないのか。(また別の項で詳しく)
・その関節をよりスムースに動かす為にどういったトレーニングを動作トレーニングやウエイトトレーニングを組み合わせて作るか。
という感じで組み立てていくことが出来ます。
ただ単に
スクワットすりゃ良いでしょ。
ということではなく、きちんと分析した上での戦略になります。時間が有限な分、こういった綿密な作業が大切です。
「動き」に関しては、私は「関節主体」で考えたほうが、よりスムースになるし、怪我もしにくいと体感しています。これは憶測ではなく、自分の怪我から通して学んだ事です。
まとめ
なんとなく、スポーツの現場って「あの筋肉が」という話題が当たり前になりますが、常に常識というものを疑っていると、新たな視点が手に入ったりします。
私も常に今の自分を半信半疑で過ごしており、その中での発見は数知れません。
これからもスポーツ医学は進化し続けます。
より日本のスポーツが活性化するために
私も何か1人でもお役に立てていけたら、これ以上嬉しいことはありません。
終わり。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。