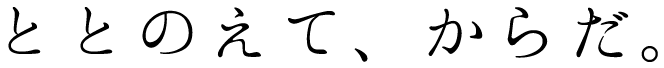どんなに痩せても二の腕だけが細くならない・・・。特に急に痩せた人や運動なしで痩せた人に多い傾向かも。
そもそも二の腕が太くなるのはどうしてなのか、それを細くしていくために出来るストレッチや筋トレ、そして食事とはどんなものなのか、解説していきたいと思います。
エステやジムに行かずとも出来るものなので是非今日から実践されてみてください。
二の腕が細くならない原因は?

二の腕が他の部位に比べて太い理由としてよく
・脂肪が溜まっているから
・皮膚がたるんできているから
というようなことが挙げられています。
今回は、じゃあどうして皮膚がたるんでしまうのか?脂肪が溜まってしまうのか?というところに焦点を当てていきたいと思います。もちろん、私たちの身体は一瞬一瞬変化し続けており、年齢と共に皮膚はたるんできます。しかし、それが年齢以上のたるみだった場合には何かしらの原因があるはずです。
運動(筋トレ)が足りない
二の腕の筋肉は特に日常では刺激が少ないのでたるみやすい部位です。腕立て伏せなど肘が伸びることに対して負荷が無いとなかなか鍛えるのは難しい。。。しかし運動(筋トレ)が足りないとその部位は緩んでいく・・・。週1~2回以上筋トレをする機会を設けていない人はまず筋力不足を疑いましょう。
姿勢の悪化が二の腕が太い原因となることも
二の腕が太い人の共通点があります。たくさんの方を見ていて気付いたことは、ほぼ間違いなく「猫背」ということです。猫背になると、相対的に背中側は伸びた状態になります。背中側に二の腕はあるので、ここもたるんでしまいますね。そして、猫背になると、重力を首と肩で受け取るようになります。肩関節から二の腕の筋肉はある(上腕三頭筋の一部)ので、ここに「力み」が溜まります。
力み=刺激なので、その刺激によって勝手に二の腕が立派に育ってしまうんですね。ということで、二の腕を適切な太さにしていくには「正しい姿勢」が不可欠なのです。
二の腕を細くする運動やポイント、食事はこれだー!
ここからは気になる二の腕を細くしていくための運動やポイント、食事を紹介していきたいと思います。どれもこれも実際のセッションでも紹介している基本的なことですが、それだけ大切なことですので是非今日から実践してみて欲しいと思います。
まずは筋トレを始めよう。簡単で効果的な運動は?
鍛えることが足りないのであればしっかりと鍛えることからはじめていきましょう。筋トレで二の腕を鍛えていく場合の種目はいくつかあります。
最初はキックバックという種目です。
(1)キックバック
こちらの動画ではダンベルで行っていますが、「家にある重いもの」なら何でも代用できるのでご自宅でのトレーニングにも取り入れてみては。
また、膝立て伏せもおすすめ。
(2)膝立伏せ


ここまで身体を沈めていきます。おへそが落ちないようにだけ気をつけていきましょう。体幹も一緒に鍛えられる種目としてはプランクからの押し上げがおすすめです。膝と肘で身体を支えます。そこから片手ずつ身体を押し上げていきます。
左右押し上げたら肘に戻ります。右手からスタートするバージョンと左手からのバージョンがあるので左右とも行っていきましょう。
(3)女性で膝立伏せが出来ない人向けの運動
それでもきつい方はこの動画で紹介されている方法なんかもおすすめ。女性は特にこういう簡単なものから始めるとよいかも。
もっと簡単に!という人は以下の「くるくるエクササイズ」がいつでもどこでも出来るのでおすすめ。
(4)二の腕くるくるエクササイズ
やり方はものすごく簡単で腕をくるくるさせながら肘を曲げて上下させるだけ。こんな簡単な運動であれば「続けられない理由は無い」と思いますので、継続していきましょう。
二の腕を細くするには「正しい姿勢」が不可欠!

ここからは姿勢を整える方法を紹介していきたいと思います。
猫背の方のポイントとしては
・身体の前側の硬さの改善
・肩甲骨の位置の矯正
これらを癖付けていくことになります。
順序を追って説明をしていきます。
ストレッチで姿勢矯正をしてみよう。
ストレッチで伸ばしたいポイントしては身体の前側です。
特に
・鎖骨を左右に広げること
・みぞおちのあたりの硬さを取ること
・肋骨の動きを回復すること
これらをしっかりすると深い呼吸が出来るようになるなどの副産物もありますので、是非チャレンジしてみてください。
といってもストレッチ方法は簡単です。
(1)座った状態で腰のあたりに両手を当てます。その手は拳を当てるか、手の甲を当てるようにしてください。
(2)そのまま、肘を締めながら(肩甲骨を寄せながら)手で身体を押し、反って行きます。みぞおちが前に突き出るような感覚です。
(3)一番きついポイントで3回深呼吸をして戻ります。
耳のちょっと下のポイント(ここが首の付け根のあたりです)が上から吊るされているような意識で背筋を楽に伸ばします。
姿勢がかなり変わるのが分かるかと思います。座っている姿勢で慣れてきたら立っている姿勢でも行っていきましょう。背筋がしゃんとし、肋骨のあたりも開いた感じがしたところで、意識を足先に移します。基本的に立つ時は意識を足先もしくは手先というように末端に置くと良いですよ。かなり安定します。
参考→姿勢矯正のたったひとつのシンプルなコツとは?立ち方座り方、その方法を徹底解説!
これらを日々の生活の中に取り入れて、姿勢の癖をつけていきます。24時間全て意識するのは無理があると思うので、1日の中で必ずする行動にセットで姿勢の意識をします。
例えば
・始業開始最初の3分は意識する
・昼休み後最初の3分は意識する
・朝の歯磨き時は意識する
等です。必ずすることとセットにすることで、高確率で習慣化することが出来ます。試してみてくださいね。こうなると「筋トレは要らないのでは?」と思うのですが、筋トレの役割というのは「身体のラインを作ること」です。ですので「より美しく」という場合には筋トレが必要になってきます。1週間?2週間?短期間で出来るものなの?人の身体が変わるのは大体数ヶ月かかります。
ですので、本当に短期間でというのははっきり言って難しいです。ただ、姿勢を癖付けることが出来ればより早く細くなるので、そういう意味でも毎日の積み重ねを大切にしてくださいね。
食べ物にも気をつけると尚スピードアップになります。
参考→3ヶ月のダイエットを習慣を味方につけて達成させる方法を食事から考えてみる。
二の腕を細くする食事って?食事は誰でもどんな目的でも共通!
二の腕という目的に限らず、食事に関しては誰もが意識する共通事項というものがあります。今回はそれを確認していくことにしましょう。
1.高タンパクな食事をすること
しっかりとタンパク質を摂取しないと体は作られてきません。いくら筋トレを頑張ったとしてもなかなか二の腕が引き締まってこないのです。
そういったことから、高タンパクな食事をしていきましょう。目安として、最低でも体重gは摂取したい。体重が60kgある人は60gのタンパク質ということになります。出来れば体重の1.5倍のタンパク質を摂取したい。
ではそれがどれくらいなのか?というと
・お肉100gでタンパク質20g
・お魚100gでタンパク質20~30g
・納豆1パックでタンパク質9g
・卵1個でタンパク質4~6g
これが大体の基準です。意外と食べないとダメだということが分かりますよね。しっかり食べないと筋肉も痩せ細るので結果としてリバウンドしやすい体になります。そうならない為にも「食べて体を作る」という意識を持っていくようにしたいものです。
2.注意すべきは(みんなが過剰摂取しているのは)脂質
脂質も必要な栄養素ではあるのですが、体が気になる人(太っている人)はこの脂質を過剰に摂取しすぎています。
脂質の目安はカロリー全体の25%〜30%ほど。実際のセッションでは細かく計算して個人差を考慮しながら出していますが、大体女性で35g~40gほどが平均的に必要な脂質です。
計算してみると分かりますが、普段食べているものを挙げてみると「食べてない」と思っている人のほとんどが「オーバーしている」んです。これはセッションをしていると本当によく分かります。意外とみなさん食べすぎなんだなって。
そしてセッションを重ねていくと「今まで、どれだけ食べすぎていたのかが分かってきました」という言葉を頂きます。
食を楽しむことはもちろん大切です。しかしそれが「食べ過ぎ」だとしたら。話をお金に置き換えるとよく分かります。お金を使って楽しむことは大切です。しかしそれが「使い過ぎ」だとしたら。
これらことを「食べることが1番の楽しみ」という人はよくよく考えたいものです。
エステに行かずに二の腕が細くなったなら。

現在、いろんな痩身エステというのがありますね。この記事での言いたいことは「姿勢や運動・食事が適切になると体重(体型)も適切になりますよ〜」ということです。こればかりは、他力ではなくて自力が必要です。そういう意味で、エステに行かずとも二の腕は細くなりますので頑張ってみてください。
二の腕を細くしたいなら、二の腕「だけ」を見ないようにしよう。
以上二の腕を細くするポイントをお話ししてきました。
特に「姿勢」というのは身体の端から端まで使うもの。
姿勢や運動、食事を正すことで、体型も正すことが出来ます。
その感覚や知識は一生ものになります。
その場限りでOKということにならないためにも。
今日から二の腕のために出来ること、しっかりと行っていきましょう!

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。