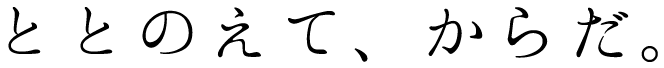普段は、身体を神経-筋のつながりや、内臓、そして関節等のつながりから整えるということを生業とさせていただいていますが、私自身も、自分の身体を見つめ始めて気をつけ始めたことがあります。
それが今回のテーマである「立ち居振る舞い(たちいふるまい)」です。「立ち振る舞い」と混同されがちですが正式には立ち居振る舞いです。
せっかく身体という物質的なものに目を向けるなら、意識も変えたいもの。立ち居振る舞いは意識しなければ身につかないですね。
今回のテーマは立ち居振る舞いです。
立ち居振る舞いって何?
立ち居振る舞いとはその字のごとく、立ったり座ったりの動作そのもののことです。
立ち居=立ったり座ったりすること。
振る舞い=身体の動かし方、ということになります。
最初に言った立ち振る舞いというのは意味が「旅立ち、門出を祝って供されるごちそう。たちぶるまい。」というものなので、似ているのですが異なりますね。
なんとなく「立ち居=立つ座る」というのは分かりますけど、「振る舞い=身体の動かし方」というのは分かりません。どういう意味なのでしょう?
振る舞うという言葉、使うとしたら「お客さんにご馳走を振る舞う」とかでしょうか。
この振る舞うの起源を調べてみると、面白いことが分かりました。
振る舞うとは「祈り」そのものである。
民俗学者の折口信夫氏の著書に「日本芸能史六講」というものがあります。
これですね。
この中に「まつり」の起源のことが書いてあります。
神様がね、他の神様を連れてくる(伴神と言うそうです)ので、その神様を饗応(酒食を振る舞ってもてなすこと。迎合すること。)することがそもそもの「まつり」の起源だったとか。
ただただ酒食を振る舞うだけではなく、舞ったりして歓迎したのでしょうね。舞いには謡いも欠かせないでしょう。これが今の伝統芸能の起こりにもなっています。
その時の立ったり座ったり。舞の中の一つひとつの動作。謡いに合わせて舞う。これがやがて「型」となります。
こういう事から、私には、立ち居振る舞いというのは、神様への態度を表すものに思えてなりません。
柔道・茶道等「道」の付くものは道場やお稽古場に神棚があるのが普通かと思います。そしてそういった芸能やスポーツは「型」や「所作」がありますよね。なるほど、伝統芸能や武道に「型」や「所作」があるのはそういうことかと、繋がった瞬間でもありました。
人対人の関係はもちろんのこと、神様への饗応もこの立ち居振る舞いには含まれているのですね。すごいです、日本人。
呼吸・代謝・排泄。立つ・座る・歩く。

人間がその生命を維持するためには、呼吸・代謝・排泄の3つが揃っていることが必要です。
ということは、シンプルにこの3つに焦点を当てることで健康ということが目指せますね。
この中で意識して改善出来るのはただひとつ。呼吸だけですね。
その呼吸をより良い、つまり深い呼吸が出来る状態にするためには?そうですね、姿勢を整えていく必要があります。
姿勢を整えて、深い呼吸が出来るようになれば、身体の隅々にまで栄養が行き渡り、要らない(使い終わった)ものは外に排出されます。栄養が巡ることで内臓の働きも正常になるので、代謝機能も正常になりますね。
私たち人間は動かなければ生活は出来ません。その動きの中で最も基本なのが立つ・座る・歩くです。つまりこれが立ち居振る舞いにつながります。
この3つが綺麗であればあるほど、姿勢も良いものであると言い換えられそう。
良く立ち・良く座り・良く歩く。
その所作は、日本の伝統芸能から学べることが、たくさんありそうです。
調えて、からだ。

現代の私たちの立ち居振る舞いというのは、まあひどいものですよね。
せっかく物質としての身体を整えるのですから、目に見えない「態度・意識」の変換も行っていきたいものです。
それが普段の所作に表れるわけですからね。
と、自分への戒めも込め、立ち居振る舞いのことをお話ししました。
ぐにゃっと背中が曲がっていたり。
動作もひとつひとつ荒々しかったり。
姿勢も動作も美しく在れば、結果的に身体への負担が減りますからね。健康まっしぐらですよ。
立ち居振る舞い。私も今日から、意識していこうと思います。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。