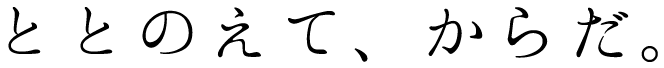肩の痛みを見ていこう
人体の関節というのは様々ありますが、その中でも特に動くのが肩関節と股関節です。よく動くということは裏を返せば不安定であるということにもなり、肩こりや四十肩・五十肩、様々な炎症が多くの人を悩ませています。
ただ、根っこの部分ではほぼほぼ同じ所から来てます。
今回は肩の痛みについて、症状であったり、原因であったりを見ていきたいと思います。具体的なエクササイズに関しては別記事を参照してください。
ただ、原因を知るだけでも解決に向かったりしますので、興味ある方は読み進めてみてください。
肩の骨格の位置を確かめよう
骨格の位置(以下アライメント)は、筋の長さが変化している可能性や、正常な運動を獲得させるために改善が必要な関節の並び方を示してくれます。
例えば、腕を体から離れるように挙げていく場合(外転と言います)、その運動を開始する時の肩関節の位置が通常よりも内側にねじれていた場合(内旋と言います)、他の人よりも動作中に外旋の動作が必要になるわけです。
この運動中に外旋動作をしないまま腕を上げていくと、腕の骨(上腕骨大結節)は肩甲骨の烏口突起という場所にある烏口肩峰靭帯と不調和を起こし、肩に痛みを生じてしまいます。
このように、アライメントの異常は正常な運動の妨げになってしまうこともあるわけです。
肩の正常なアライメントチェック
首と肩の付け根の辺りに、「ぽこぽこ」した出っ張りがありますよね?それ、頸椎と胸椎の境目なんですが、その高さよりも少しだけ両方の肩が下にある状態がアライメントとしては正常とされています。

例えば上の写真の場合だと、右は少しだけ下にあるのでOK、左は分かりやすく下がりすぎにしてみました。
こういうアライメントの場合、その下がりすぎに関わっている筋肉を刺激し、アライメントを改善していこうかなとこう考えます。
また、横から見たら、肩の頂点にある出っ張りが、ちょうど体を前後に2分割する位置にあることが正常だとされています。

このようなイメージです。
肩甲骨の正常なアライメントチェック
肩甲骨は専門的な用語が連発するので、端的に言うと「肩甲骨の内側のラインと背骨が平行かどうか」というのをチェックポイントにすると良いかと思います。これならチェックしやすいですよね。
これを基準に肩甲骨の位置がどうずれているのかを観察すると、「どう直すか」が見えてきます。
肩関節の機能障害により起こる症状について
肩関節を構成する肩甲骨や上腕骨、そして胸椎などの位置が何かの原因により変化してしまうことにより、様々な症状が起こります。
代表的な症状を見ていきます。
四十肩・五十肩
正式には肩関節周囲炎と言われていますが、原因が明らかではないというのが今の医学での現状です。
こういう方が以前来ましたが、後述する内臓のダメージ(元を辿るとストレス)から改善へのアプローチをしていくと快方に向かって行きました。
肩関節を構成する筋や腱のうちのどれかの炎症
上腕二頭筋長頭腱炎などがそれにあたるかと思います。この場合もオーバーユース(使いすぎ)以外の場合には、アライメントの崩れから始まっていることがほとんどです。
そしてそのアライメントの崩れの原因が、後述するところにあること(あったこと)が臨床ではほとんどです。
その他頸椎などから来るもの
頸椎から肩や腕の筋肉につながる神経は出ているので、その流れが悪くなることにより痛みや痺れが出る方が多いです。
その場合はしっかりと「身体全体」そして「生活全体」を見てベストなアプローチを決めていきます。
違う箇所から肩周辺の崩れや機能障害が発生することも
肩の痛みや動かしづらさだからといって、肩ばかりみるのははっきり言って視野が狭いです。臨床上外傷を除いて肩が痛いと言って肩をケアしていくということはほとんどありません。
とりあえず痛いからと言って湿布や痛み止めという処置になると、まあほぼほぼ間違いなく後に引きます。その部分が治っても他の部分にしわ寄せが出ます。
骨盤帯からのもの
骨盤帯が前後左右どこかに角度がずれるとそのずれのバランスを取ろうとして上体へ波及していきます。
例えば骨盤の右側が上がっている場合、それとバランスを取るように右肩は下がるといった感じです。(もちろん左肩が下がるケースもありますよ。)
このようなことは往々にしてあり得るために、肩「だけ」を見るのは非常に危険で安易だということです。
骨盤のくずれ(歪みではなくてくずれとあえて表現します)が気になる人で肩の凝りや痛みがある人はここから起こっているかもということを疑っても良いかもしれません。
足根骨の位置不全から起こるもの
足根骨とはいわゆる「足の骨」のことですが、この骨のどれかが位置不全、つまりズレてしまうことにより(主にアーチがつぶれるような状態が多いです)、足という土台のバランスがおかしくなり、膝、股関節、背骨と波及し、結果として肩こりが出たという人もいます。

この場合には、足根骨のずれている骨に対してアプローチをし、足という土台をしっかりさせた上で、その骨格を安定させていく(染み込ませていく)トレーニングをしていく必要があります。
治療やリハビリについての流れ
一般的に「肩が痛い」という場合の治療やリハビリの流れについて確認をしていきたいと思います。ちなみに私はこのような施術は導入として利用する程度で、ほぼしません。自分の臨床上の経験により、肩の痛みの原因はもうちょっと違うところにあるなあと感じているからです。
ただ、程度が軽い人はこれらの治療やリハビリで十分痛みが取れると思います。
難しいことを書いてますがYoutube先生に「肩こり ストレッチ」て聞けば色々と出てくると思いますよ。程度の軽い人は本当にそれで十分です。

機能的と構造的、二つからのアプローチが必要
機能的に、肩関節のどの動きが辛いのか、痛いのかを認識した上で、その動きに関する筋肉のバランスを整えていくのが一般的な改善策です。
肩を回すのが辛いならば「一番辛い瞬間はどこか」を探り、その時の肩甲骨の動きで肩関節の動き方を判断します。
シンプルに考えると、痛い動きの反対の動きを行って、それに関する筋を活性化させ、肩甲骨の位置を左右で同じにしていくよう心がけていきます。
例→肩を後ろへ引く動作(背中を寄せる動作)で痛いならば、肩を前へ出す動作(胸を寄せる動作)でトレーニングを行い、前後でのバランスを取るなどです。
これにより、機能と構造の2つを安定させます。
最終的には筋反射チェックなどを行い、左右の筋出力のバランスが同じかどうかをチェックしていきます。
経絡の滞りが原因の方はリリーストレッチが効果あるかもしれません。
肩こりだけではなく便秘や肌荒れにも!肩のリリーストレッチでスッキリ爽快♪
バランスを整え、動作のパターンを染み込ませていく
機能・構造的なバランスが取れたならば、そのまま理想的な動作パターンを染み込ませていく作業に移ります。理学療法士の方々はこれが得意かと思います。
要は、理想的な運動パターンとの乖離(腕の上げ方が解剖学的にズレてるよ〜という意味です)が続いた時に私たちは痛みを生じ、それらを修正していくのがリハビリだ〜となるわけです。
ので、まずは何も負荷のかかっていない上体で腕を横に上げる、万歳をするなどの動きを丁寧に身体に覚えこませ、それに負荷を加えていくことでその動きに関わる筋肉を鍛え、より強い刺激で神経-筋の動作パターンを確かなものにしていきます。
ここまでリハビリなどを見てきたけど・・・
色々な方法で肩のくずれを直したりして痛みを取っていくということを見てきましたが、そもそも肩を痛めてしまった原因というのはどこにあるのでしょうか?
ただただ「姿勢が悪い」だけではないかもしれません。
肩を痛めたそもそもの原因は?
外傷の場合
外傷の場合には、RICE処置を施し、まずは回復を待ちます。その後でダメージを受けている関節そのものや関節の機能をリハビリしていきます。
打撲や捻挫の場合には他の関節同様に「ロックを外す」作業が必要になってくるかと思います。人によりどうロックがかかっているかは人により様々ですので、詳細は省きます。
姿勢のくずれから来る場合
姿勢の崩れからくる場合には、最初に記した機能障害に関してのアプローチをしていくことが必要になります。どのあたりの崩れからくるものなか、それを神経-筋のアプローチから治しても良し、関節や骨へのアプローチで治しても良し。
どんな方法で改善していくにしろ、「筋バランス」と「筋反射の出力」をしっかりさせていくことが課題となってきます。
ただ、崩れが出ているというのはあくまでも「結果」であり、その奥には「原因が潜んでいる」ので、その部分を明確にしていく必要が有ります。
内臓のダメージはどうか
内臓のダメージを見ていくことで、先述した身体の姿勢の崩れ、崩れの「なぜ」の部分がより見えるようになってきます。どこの内臓がダメージを受けているのかは
- 痛んでいる部位での判断
- 崩れのせいでコリが発生している椎骨(背骨の骨)での判断
- 経絡での判断
と色々あるので、ひとつひとつ見ていきたいと思います。
痛んでいる部位での判断について
肩の痛みを観る時には、肩甲骨を基準にしてみています。
肩甲骨を上下に分け、上側が痛ければ「肺」のエネルギーのダメージ、下側が痛ければ「心」のエネルギーのダメージです。
その部位を明らかにした上で、なぜその対応する内臓のエネルギーがダメージを受けているのかを色んな観点(生理・物理・心理面)から分析をしていきます。
色んな観点の分析については最終的にはどのアプローチでも辿り着くところであり、現在の私のセッションの根幹な部分でもあります。この分析法にたどり着けたのは本当にご縁が運んでくれたものです。
くずれのある椎骨(背骨の骨)での判断
肩に関わるのは頚椎や胸椎ですが、それらのどこが一番変位や固着が起こっているのかを観ていき、その部分に対して対応する内臓や筋へのアプローチをしていきます。
例えば胸椎の3番目のくずれによるコリがひどい場合には、そこは内蔵でいうと「肺」に関係するので、肺エネルギーに関する反射点を使うのか、肺エネルギーに関連する「三角筋」という筋肉を刺激することで改善していくのか、場合によってですがそういう風にアプローチしていき、内臓エネルギーの活性化を図ります。
経絡での判断
これに関しては先述の”痛んでいる部位での判断”とほぼ被ります。痛んでいる部分の点がどの経絡を通るのかでその経絡に対応するエクササイズやストレッチをしていきます。
内臓のダメージから見えてくるもの
こういった、内臓のダメージを観ていくことで見えてくるものがあります。それは、その人の生活の仕方そのものです。生理・物理・心理の観点から見ていくということは、日頃どう身体や心を動かしているかというところにつながります。
動作パターンを理想的にしたのに治らない、くずれを直したはずなのに肩こりが取れないという人は最終的には、ここに原因があるのだと感じます。
どういった種類のストレスで人はダメージを受けてしまうのでしょうか。例を挙げます。
肺エネルギーのダメージの場合
キーワードとしては「ねばならない」です。こういった心理状態や環境があるならば、その状況で対応する内臓エネルギーや経絡という川の流れに滞りが起こり、結果として肉体に痛みが生じます。
生活の中での過剰な「ねばならない」義務感・正義感・規律などがある場合には肩こりが出やすいんですよ。緊張しちゃうとかね。

昨日いらっしゃった方もね、「なんだか最近いきなり肩が」ということだったんです。
アライメントを正すような運動は頑張ってらっしゃる方。もちろんアライメントチェックしても肩は正常な位置にありました。
じゃあなんでだろう?そこで先ほどの「ねばならない」に目を向けるんです。
もしかして最近、張り詰めて生活してません?
とこう、話しを進めていくわけです。
今までもなんとなく内臓の感情のつながりについては資格を取るまでの勉強で習ってはいましたけど、ここ最近はよりその関係性についての思いが強くなりました。
まとめ
一言に「肩の痛み」と言っても、症状はたくさんあります。そして原因の部分になると症状以上にたくさんあります。なんせ「生活全体」で見たらそりゃあ無限にありますからね。
ただそうやって「健康は普段の生活から作るもの」という意識が芽生えるだけでも、小手先のストレッチとかではなくて、もっと大きな視点で健康というものを捉えることができていくのではないかとそう思って日々お客様に接しています。
見える症状から見えない生活全体にまで目を向ける。自戒の念も込めて、肩の痛みについて書いてみました。ストレッチ等は全力で作成中です!しばしお待ちを!

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。